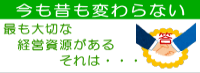�u�o�c�x���ƃT�|�[�g�v�u�⌾���E�����̑��k��葱���Ə��ލ쐬�v�̏��эs�����m�������i�����s���撆���j�ł��B

�m���Ă������������̂���knowledge
�u�������v��u�ˑR�v�ւ̔����B�����ł���ĂȂ����߂ɁB
 �@�������ւ̔����B�ˑR�ւ̔����B�Ƒ��̎��A�����鑊���ɂ��Ēm���Ă����������Ƃł��B
�@�������ւ̔����B�ˑR�ւ̔����B�Ƒ��̎��A�����鑊���ɂ��Ēm���Ă����������Ƃł��B�@�ł́A�����Ƃ͉��ł��傤�B�����Ƃ́A���@�Œ�߂�ꂽ�����l���A�S���Ȃ����l�̍��Y�R�Ɉ����p�����Ƃł��B�Ⴆ�A��ʓI�ȂS�l�Ƒ���z�肷��ƁA�����S���Ȃ����ꍇ�ɂ͔z��҂ł����ƂQ�l�̎q�����̍��Y�R�Ɉ����p���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���܂��́��u���葱���i���`�ύX���j�̓����҂Ƃ��Ă���ĂȂ����߂Ɂv
�@��������������ƁA�a�����A�s���Y�i�y�n�⌚���j�Ȃǂ̌̐l�̍��Y�́A�����l�S���̋��L���Y�ƂȂ�܂��B���̂��߁A�̐l�̍��Y�ɂ��āA�����l���`�ւ̕ύX�葱�����Ȃ���Ȃ�܂���B�����̎葱���A�����������ԂƑ̗͂����߂��܂��B�����̎葱���ɂ́A�̐l�i�푊���l�j�̏o�����玀�S�܂ł̌ːГ��{�A�����l�S���̓��ӏ����ӏؖ����A��Y�������c���Ȃǂ��K�v�ɂȂ�܂��B�������̒ʂ�A��������Z�@�ւ̑����͕��������ł��B
�@�܂��A�̐l�̂������ł̗̑͏��ՂƔ߂��݂����钆�Ŏ葱��i�߂Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�X���[�Y�Ɏ葱��i�߂邽�߂ɂ́A���O�ɑ����ɂ��Ă̒m���������Ă������Ƃ��]�܂����ł��B
�����Ɂ��u�Ƒ��i�����l�j�ԂŃg���u���ɂȂ�Ȃ����߂Ɂv
 �@�u�����v���u�����v�ɂȂ�B�Q���ԃh���}�ł悭�ڂɂ��邠��ł��B�傫�Ȏ��Y�������͎҂��S���Ȃ�A���̈ꑰ�ō����̑������N���镨��ł��B���́u�����v�A�h���}�̐��E�⎑�Y�Ƃ����ł͂Ȃ��A������ʓI�ȕ��ʂ̉Ƒ��ɂ����Ƃ��Đ[���ȑΗ����N���邱�Ƃ�����܂��B�Ȃ�Ƃ��b�������ʼn����ł���Ηǂ��̂ł����A�ٔ��܂ł����ƂȂ�Ǝ��ԁA��p�A�̗͂�傫����₷���ƂɂȂ�܂��B
�@�u�����v���u�����v�ɂȂ�B�Q���ԃh���}�ł悭�ڂɂ��邠��ł��B�傫�Ȏ��Y�������͎҂��S���Ȃ�A���̈ꑰ�ō����̑������N���镨��ł��B���́u�����v�A�h���}�̐��E�⎑�Y�Ƃ����ł͂Ȃ��A������ʓI�ȕ��ʂ̉Ƒ��ɂ����Ƃ��Đ[���ȑΗ����N���邱�Ƃ�����܂��B�Ȃ�Ƃ��b�������ʼn����ł���Ηǂ��̂ł����A�ٔ��܂ł����ƂȂ�Ǝ��ԁA��p�A�̗͂�傫����₷���ƂɂȂ�܂��B�@���Љ�ł̉Ƒ����͑��l�����Ă���A�Ƒ��ł����Ă��ЂƂ�ЂƂ�̐����`�Ԃ͈Ⴂ�܂��B�Ƒ��i�����l�j�Ԃł̃g���u������̂��߂ɂ��A�����l�ɂȂ�̂͒N�ŁA���ꂼ�ꂪ�ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂��b�������Ă������Ƃ͑�ł��B���Y�Ƃ������������������ɉƑ��W���M�N�V���N���Ă��܂��͎̂c�O�ł��B��͂�A�摗�肹�����߂̑Ή��Ɍ���܂��B
�������ā��u�����ɂ�������������v
 �@���Y�������p���ɂ��A�������|��܂��B�����łł��B�i���`�ύX���̏��葱���ɂ��萔���Ȃǂ��|��܂����A����قǐS�z�͂���܂���B�j�����̏������K�v�Ȃ̂́A�s���Y�ł��B���Y�Ƃ��āA�y�n�⌚���������p���ꍇ�ł��B
�@���Y�������p���ɂ��A�������|��܂��B�����łł��B�i���`�ύX���̏��葱���ɂ��萔���Ȃǂ��|��܂����A����قǐS�z�͂���܂���B�j�����̏������K�v�Ȃ̂́A�s���Y�ł��B���Y�Ƃ��āA�y�n�⌚���������p���ꍇ�ł��B�@�����ł́A��b�T���z���傫�����߁A�����Q�R�N�x�ł́A�S���Ȃ����l�̂��������ł��ېł��ꂽ�l�̊����͖�S���ł����B�������A�����Q�V�N����ېōT���z�������������A�ېőΏێ҂̊����������Q�R�N�̖�P.�T�{�̂U�����炢�܂ŏオ��ƌ����܂�Ă��܂��B���Y�Ƃ����̖��ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B�����ł������Ȃ�����s���Y�p������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�Ȃ��悤�ɑ����ł�������A������Ȃ����炢�͔c�����Ă����Ɨǂ��ł��傤�B
�@���A�s���Y���Ȃ��Ă��a�����⊔���Ȃnj����ɑ���������Y�������ꍇ���A�����ł̏����͕K�v�ł��B�������A���̏ꍇ�͂��̈����p���a�������Ŏx������̂Ŗ��Ȃ��P�[�X�ł��B
�y����̎葱���z�����������ɂ��邱�Ɓ@�`�⑰�̂��߂ɂ��`
 �@��������܂��B����[�A����Ȃɂ���́I�H�Ƃ��������ł��B�������A�����̎葱���͎������S���Ȃ������̎葱���ł��̂ŁA�����ōs���K�v�͂���܂���B�c���ꂽ���Ƒ��i�⑰�j���s���葱���Ȃ̂ł��B
�@��������܂��B����[�A����Ȃɂ���́I�H�Ƃ��������ł��B�������A�����̎葱���͎������S���Ȃ������̎葱���ł��̂ŁA�����ōs���K�v�͂���܂���B�c���ꂽ���Ƒ��i�⑰�j���s���葱���Ȃ̂ł��B�@���O�̏����Ƒ�i��D�ی��؏���_�����ڂ��ĂP�̃t�@�C���ɂ܂Ƃ߂Ă����j�ɂ��A�c����邲�Ƒ��̕��S�����炵�Ă������Ƃ��A������Ƃ����v������ł��ˁB
�������ł́A�l��������̂��ׂĂ���Ă��܂��B
�@���L�̓��A�K�v�Ȏ葱���y�ъY������葱���s�����ƂɂȂ�܂��B
| ��{�I�Ȏ葱�� | |||
|---|---|---|---|
| ���S�� | ���̉Α����\�� | �Z���[������ | ���ю�ύX�� |
| �����̎葱�� | |
|---|---|
| �⌾���̌��F | ���������̐\�q |
| ���I�ی��E���I���i�̒�~�葱�� | ||
|---|---|---|
| �N���̒�~ | ���ی����i�̒�~ | �ٗp�ی��̒�~ |
| ���I�ی��E���I���i�̐����葱�� | |||
|---|---|---|---|
| �⑰��b�N���̐��� | �Ǖw�N���̐��� | �⑰�����N���̐��� | �⑰�⏞���t�̐��� |
| ���S�ꎞ���̐��� (�����N��) |
�������⏕���̐��� (���N�ی��g��) |
�����⏕���̐��� (�D���ی�) |
���Ք�̐��� (�������N�ی�) |
| �������̐���(�J�Еی�) | ���z�×{��̐��� | ||
| �ŋ�����ѐ����ی��̎葱�� | ||
|---|---|---|
| �����ŏ��m��\������є[�� | �����ł̐\������є[�� | �����ی����̐��� |
| ���Y���L���̈ړ]�ɔ����葱���i���`�ύX�j | |||
|---|---|---|---|
| �s���Y | �a���� | ������ | �d�b������ |
| �ؒn������ �s���Y�Ɋւ��錠�� |
����(����) | �S���t����� | |
| ���̑��̎葱�� | ||
|---|---|---|
| �l���Ǝ�̔p�Ɠ� | ���K�͊�Ƌ��ϓ��̎��� | �m�苒�o�N�����̐��� |
| ���̑��̎葱�� | |||
|---|---|---|---|
| �^�]�Ƌ��̎��� | ���������̒�~�E���`�ύX (�d�C�E�K�X�E�����ENHK) |
�N���W�b�g�J�[�h�̉�� | �p�X�|�[�g�̎��� |
| �g�ѓd�b�̉�� | �v���o�C�_�[���l�b�g �֘A�̉��A���`�ύX |
��z�T�[�r�X���̊e�� �T�[�r�X�_��̒�~ |
���{�݂̉�� |
| �u���O��r�m�r�̒�~�E�p�� | |||

�⑰�̂��߂ɂ��A���O�ɁA�ꗗ�\�ɂ��Ă����܂��傤�B
�@�a���������̐���
�A�������Ă���ی��̐���
�B�e��_���T�[�r�X���e�̐���
��s�̎�����e�A�ی��،��A�e�_��̏��ނ��t�@�C���ɂЂƂ܂Ƃ߂ɂ��Ă����܂��傤�B
�������̏̐������ł����ɁA�⑰�̕��S���y���ł���c�[���ɂȂ�܂��B
���ɁA����̏��葱�������n��ŋL���܂��B
�������J�n�����ƁA���l�Ȏ葱�����������܂��B
�͏o��\���̎葱���ɂ́A
�@�@��������߂��Ă���葱
�@�A�����͒�߂��Ă��Ȃ����A���₩�ɐi�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��葱��
������܂��B�ȉ��A�葱����������ɑ����J�n��̎葱���ɂ��āA���n��ŋL���Ă݂܂��B

�͏o��\���̎葱���ɂ́A
�@�@��������߂��Ă���葱
�@�A�����͒�߂��Ă��Ȃ����A���₩�ɐi�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��葱��
������܂��B�ȉ��A�葱����������ɑ����J�n��̎葱���ɂ��āA���n��ŋL���Ă݂܂��B

�@�����J�n��̎葱�����X���[�Y�ɍs�����߂ɂ��A�ǂ̂悤�Ȏ葱��������̂��̑S�̑���m���Ă������Ƃ���ł��B
 �@�����āA�����̎葱�����X���[�Y�ɍs����Ԃ̃|�C���g�́A�����l�S���̊Ԃő������Y�̕������̃R���Z���T�X�i�A�g�ƍ��Ӂj���ł��Ă��邱�Ƃł��B�����̎葱���ł́A�����l�Ԃł̗����������Ă���Ƃ����؋������߂��܂��B���̏؋��Ƃ��Ď葱���ɂ́A��Y�������c���⑊���l�̌ːГ��{�Ȃǂ̏��ނ̒�o�����߂��܂��B
�@�����āA�����̎葱�����X���[�Y�ɍs����Ԃ̃|�C���g�́A�����l�S���̊Ԃő������Y�̕������̃R���Z���T�X�i�A�g�ƍ��Ӂj���ł��Ă��邱�Ƃł��B�����̎葱���ł́A�����l�Ԃł̗����������Ă���Ƃ����؋������߂��܂��B���̏؋��Ƃ��Ď葱���ɂ́A��Y�������c���⑊���l�̌ːГ��{�Ȃǂ̏��ނ̒�o�����߂��܂��B
�@��͂�A�X���[�Y�Ȏ葱���̂��߂ɂ��A�����J�n�O�̒i�K�ŁA�Ƒ��Ԃō��Y����Y���ǂ̂悤�ɕ����邩�Ƃ����b���������ł��Ă��邱�Ƃ��A�ƂĂ��傫�ȃ|�C���g�ƂȂ�܂��B
 �@�����āA�����̎葱�����X���[�Y�ɍs����Ԃ̃|�C���g�́A�����l�S���̊Ԃő������Y�̕������̃R���Z���T�X�i�A�g�ƍ��Ӂj���ł��Ă��邱�Ƃł��B�����̎葱���ł́A�����l�Ԃł̗����������Ă���Ƃ����؋������߂��܂��B���̏؋��Ƃ��Ď葱���ɂ́A��Y�������c���⑊���l�̌ːГ��{�Ȃǂ̏��ނ̒�o�����߂��܂��B
�@�����āA�����̎葱�����X���[�Y�ɍs����Ԃ̃|�C���g�́A�����l�S���̊Ԃő������Y�̕������̃R���Z���T�X�i�A�g�ƍ��Ӂj���ł��Ă��邱�Ƃł��B�����̎葱���ł́A�����l�Ԃł̗����������Ă���Ƃ����؋������߂��܂��B���̏؋��Ƃ��Ď葱���ɂ́A��Y�������c���⑊���l�̌ːГ��{�Ȃǂ̏��ނ̒�o�����߂��܂��B�@��͂�A�X���[�Y�Ȏ葱���̂��߂ɂ��A�����J�n�O�̒i�K�ŁA�Ƒ��Ԃō��Y����Y���ǂ̂悤�ɕ����邩�Ƃ����b���������ł��Ă��邱�Ƃ��A�ƂĂ��傫�ȃ|�C���g�ƂȂ�܂��B
���ɁA�������Y�́u�ΏۂɂȂ���́v�u�ΏۂɂȂ�Ȃ����́v�ł��B
���Y�̎�ނ͂�������܂��B
�����ł́A�������Y�̑�\�I�Ȃ��̂ɂ��āA���ނ��Ă݂܂��B
�����ł́A�������Y�̑�\�I�Ȃ��̂ɂ��āA���ނ��Ă݂܂��B

�@���Y�̕������ɂ����āA���Ɉӎ����Ă������������̂́A�s���Y�ł��B�s���Y�́A�ϓ��ɕ����邱�Ƃ�����Ƃ�������������܂��B
�@���K�́A�R�O�O���~�ÂłR�l�ŕ����������Ƃ��ł��܂��B�������A�s���Y�͂R���̂P�ÂƂ��������ł̕������i���L�̎����j�ɂȂ�܂��B�P�̕��̂������ŕ����邽�߁A�����ł̏��L�ƂȂ�A���̏����ɂ��Ă͋��L�ҊԂ̍��ӂ��K�v�ɂȂ�P�[�X�������Ȃ�܂��B���p�����K�Ɋ����ĕ����������@������܂����A�Z���Ƃ��Ďg�p����Ƒ����������A�Ȃ��Ȃ������������Ȃ��̂������ł��B
�@�Ȃ��A�������̒Ⴂ���Y�ɂ��ẮA������`�������Ƃ����������Ō̐l�̎v���o���ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@���K�́A�R�O�O���~�ÂłR�l�ŕ����������Ƃ��ł��܂��B�������A�s���Y�͂R���̂P�ÂƂ��������ł̕������i���L�̎����j�ɂȂ�܂��B�P�̕��̂������ŕ����邽�߁A�����ł̏��L�ƂȂ�A���̏����ɂ��Ă͋��L�ҊԂ̍��ӂ��K�v�ɂȂ�P�[�X�������Ȃ�܂��B���p�����K�Ɋ����ĕ����������@������܂����A�Z���Ƃ��Ďg�p����Ƒ����������A�Ȃ��Ȃ������������Ȃ��̂������ł��B
�@�Ȃ��A�������̒Ⴂ���Y�ɂ��ẮA������`�������Ƃ����������Ō̐l�̎v���o���ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�s�����m�������g�b�v�b���������̍s�����m�b�o�c�x���T�[�r�X�b�Ɩ��Ɨ����ē��b���₢���킹�b�������b�m���Ă������������̒m���b�v���C�o�V�[�|���V�[
�R�����g�b�v�b�R�����b�����T�[�r�X�b���ƌv�揑�̏������i�O�ҁj�b���ƌv�揑�̏������i��ҁj�b����Љ�Ɛ��N�㌩���x�`�F�m�Ǎ���҂̕ی�` �b�В��̍���Ɖ�Ќo�c�̎���